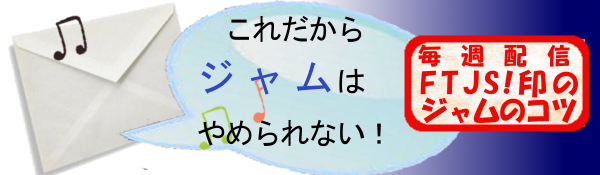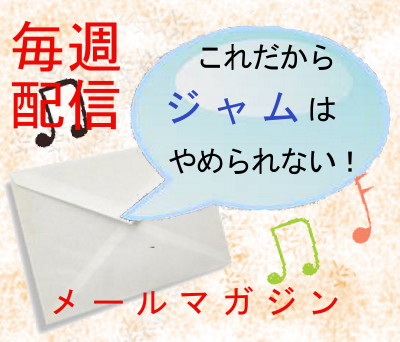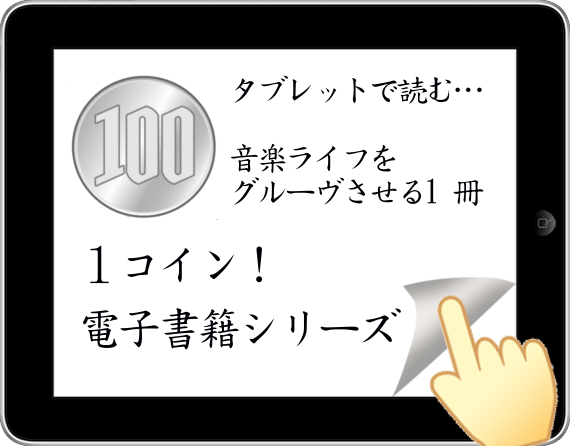毎回、アドリブセッションの視点から、
初心者に必要な音楽理論や知識をわかりやすく解説しているこのブログ。
今回も、シリーズで続いている音感話の第6弾です!
音感はアドリブする上でとっても便利な能力です。
でも、音感が身に付いたからといって、
実はアドリブはできるようになりません。
いくら完璧な相対音感を身につけても、
実際にセッションをしない人は絶対にアドリブは上達しません。
これもまた、厳然たる事実なのです!
クラシック出身で完璧な絶対音を持っている人も、
吹奏楽をやっていて、完璧な相対音を持っている人も、
アドリブになると、まったくダメな人が、世の中に沢山います。
逆に、音感なんてなくても、
自由に楽しくバンドと会話をしてしまえるプレイヤーも実は存在します!
ですので、部屋に閉じこもって、苦労して相対音を身につけても、
「頑張ったね。それで?」
という結果になりやすいことをしっかり覚えておいて下さい。
アドリブセッションにおいて便利な相対音感ですが、
絶対に必要なものでは決してありません。
そのあたりのバランスをしっかり取りながら、
少しづつ実践していって頂けたら幸いです。
======================================================
▽無料メルマガの登録はここから
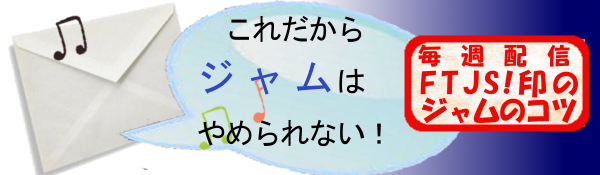
======================================================
毎回初心者向けに、ジャムセッションの視点から
わかりやすく音楽理論をお伝えしているこのブログ。
今回もここのところのシリーズ展開である「相対音感」について
ガンガンお伝えしていこうと思います。
今回のテーマは「半音はどうやって歌えばいいの?」
相対音は、ドレミの相対音を、
歌詞のように付けて歌うことによって身に着きやすくなる!
というお話を、過去の記事ですでにしました。
でも、#や♭などの臨時記号がつくと、
どうしても「どしゃーぷ~」などのような発音になり
一音節で歌うことができないため、メロディに追いつかなくなります。
このような場合の隠れたコツが実はあります!
まず英語表記でドレミファソラシドを把握します。
Do Re Mi Fa So La Ti Do
で、この小文字の部分を
『 i 』に変えたら#、『 e 』に変えたら♭というルールを適用します。
たとえば、ミ♭ならば、
MiがMeになるので、「メ」という発音になります。
たとえば、レ#ならば、
ReがRiになるので、「リ」という発音になります。
こういう風に半音を処理すれば、
全ての音を一音節で発音できるため、とても歌いやすくなります!
「ドレミミふらっと~」と歌わなければいけないメロディが
「ドレミメ」という風に、全て一音節できれいに歌えるわけです!!
ただし、ここからが一番の注意点!
ここまで細かく把握すれば、
確かに歌いやすくなるし、相対音感もさらに身につきやすくなります。
が!
はっきり言って、この歌い方に慣れるまでかなりメンドクサイです!
ですので、いきなり受験勉強的に全て覚えようとするのではなく、
まずは簡単で短くて、なじみのある半音を使ったメロディから
少しづつ攻略して、慣れていくことが肝心です。
(まずは♭系メロディ、それから#系メロディの順番が特にお勧めです。)
しっかり半音を歌い分けられれば、
さらに相対音感は身に着きやすくなります。
ご興味のある方は、是非試してみてくださいね!
======================================================
▽無料メルマガの登録はここから
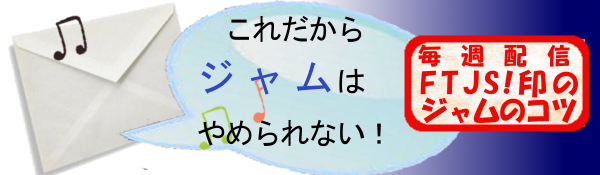
======================================================
毎回、セッションに役立つ音楽理論や知識を、
初心者にも分かりやすく解説しているこのブログ。
今回は相対音を身につけようシリーズ第4弾!
特に、鍵盤楽器や、管楽器プレイヤーにとって
相対音感を意識しやすくするコツについて解説します。
鍵盤というのは、
左から右に行けばきれいに音程が上がっていって、
しかも、各鍵盤の音が見た瞬間に分かりやすい特徴を持っています。
また、サックスやトランペット、クラリネットなど、
多くの管楽器は、もともとのチューニングがキーCでできていない
「移調楽器」という特徴をもっています。
これらの特徴というのは、
様々な楽器が集まっていっせーの!で演奏するジャムセッションでは、
かなりネックになることが多いです。
しかも、相対音を身につけようとして、
ドレミを歌詞のようにふっても、楽器の構造上、
それが実音なのか、相対音なのか混乱しやすい原因にもなっています。
そこで、ピアノや移調楽器をプレイしている人は、
ドレミを数字でとらえなおしてしまいましょう!
ド レ ミ ファ ソ ラ シ ド
1 2 3 4 5 6 7 8
という風に、数字で考えてしまうのです。
ドレミファミレドは1234321です!
そうすると、「実音はファだけど、相対ではドで…。」
なんてぐちゃぐちゃ頭の中でやらなくても、
パッと誤解が少なく数字を歌うことができます。
また、実音のとらえ方がずれている楽器が集まるセッションでは、
この数字でよくコード進行や、メロディをやりとりします。
数字だと、どの楽器にとっても
誤解のない、とても便利な共通言語になるからです!
相対音を身につけやすくするのはもちろん、
今後のセッション人生をよりスムーズに楽しむためにも、
是非数字でドレミをとらえなおす方法に慣れておいてくださいね。
======================================================
▽無料メルマガの登録はここから
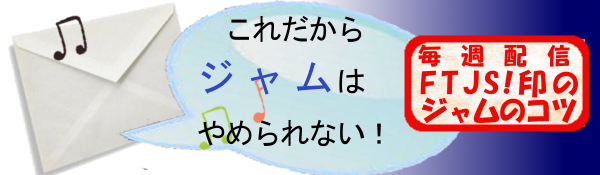
======================================================
毎回セッション的視点から、初心者に分かりやすく
音楽理論や知識をお伝えしているこのブログ。
今回も、前回に引き続き、
アドリブセッションに便利な相対音感の身につけ方をお伝えしていきます!
相対音感とは、読んで字のごとく、
何かの音を中心にして、そこからどれだけ離れているのかがわかる音感のこと。
つまり、一度自分の中で「この音がドだ!」
と決めてしまえば、あとはずっと、そのドの音を中心に
ドレミが聞こえてくる耳のことをいいます。
逆にいえば、ドを中心にして、
ドレミを歌い分ける練習をすればおのずと相対音感は身に着きやすくなります!
なので、ラララで歌うのが癖づいてきたら、
さらなる基礎編としては、「ドレミを歌詞のように付けて歌う」
という練習をすれば、さらに相対音感はものすごいスピードで身についていきます。
この時大事なのは、「ドの音は、実音上はどの音でも大丈夫」ということ。
ピアノのドの音を絶対にド!と歌うのではなく、
たとえば「キーFの曲のメロディだよ!」と言われたら、
Fつまりファの音をドと捉えなおして、相対音の歌詞をつけましょう。
始めは慣れないかもしれまえんが、
少しづつ実践していくと、ほぼ自動的に頭の中で変換されるようになります。
また、この自動で変換されるくらいまで歌い慣れてくると、
その時点で童謡などのシンプルなメロディは
自然とドレミで聞き取れる耳が出来上がっていると思います。
まぁ、実際は完璧な相対音がなくてもセッションは楽しめるので、
焦らず少しづつ、楽しみながら練習することが、この手の練習のコツです。
是非自分の耳をガンガン活用してあげてくださいね!
======================================================
▽無料メルマガの登録はここから
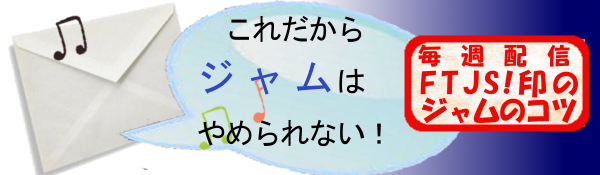
======================================================